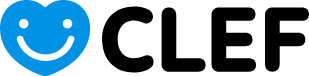2026年1月施行 取適法(中小受託取引適正化法)とは?下請法との違いは?要点をホームページ担当者向けにわかりやすく解説
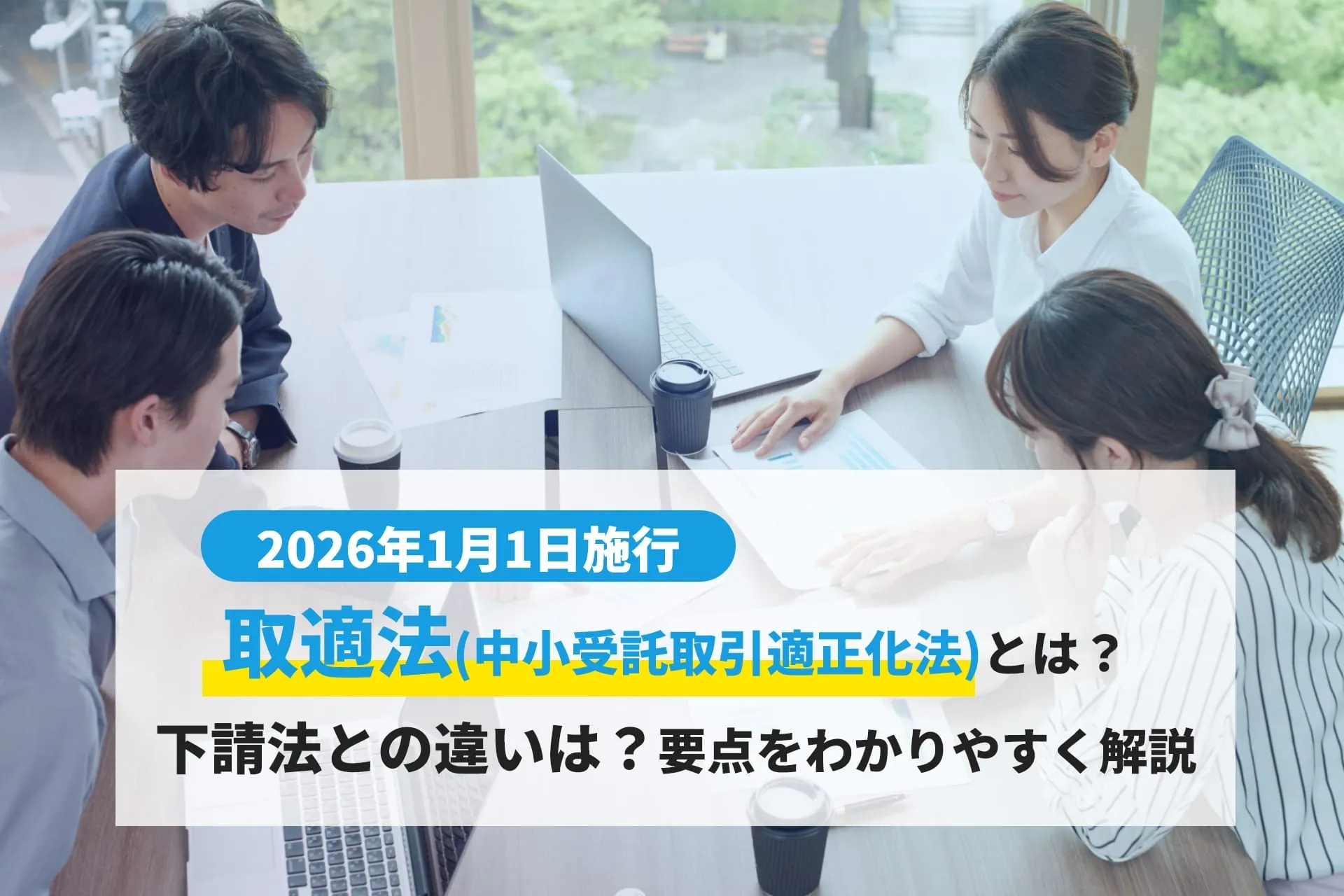
(監修:株式会社クレフ マーケティングチーム)
ホームページのリニューアルや記事コンテンツの作成などを外部パートナーへ発注する仕事は、多くのWEB担当者にとって日常業務と言えるでしょう。 その一方で、2026年1月1日に施行予定の「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」によって、こうした業務委託のルールが大きく変わることは、まだそれほど知られていません。
これまでなんとなく行ってきた依頼の仕方や、曖昧な条件での発注が、今後は法律違反と評価される可能性があります。 この記事では、取適法と従来の下請法の違いを押さえながら、WEB担当者がどのような準備をしておけばよいかを整理します。ポイントを理解しておくことで、法令を守りつつ、自信を持ってホームページの発注に臨めるようにしていきましょう。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
目次
取適法とは(中小受託取引適正化法)?2026年施行の背景と概要
ホームページ制作やシステム開発の現場では、発注する企業側と制作会社・フリーランスなど受注側との間で、どうしても力関係に差が生じがちです。従来の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、こうした不公正な取引を是正するための法律として長く機能してきましたが、主な対象は製造業や建設業など、重層的な下請け構造を前提とした業種でした。
一方で、今日のWEB業界では、個人のデザイナーやライター、エンジニアなどが、会社に所属せずに仕事を請け負うケースが増えています。こうした新しい働き方は、従来の下請法の想定から外れている部分も多く、実態に合った保護が十分とは言えない面がありました。
そこで下請法を大幅に見直し、名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へと改め、対象範囲やルールを現在の取引環境に合わせて整理し直すことになりました。2026年1月1日の施行後は、これまで以上に中小企業・個人事業主との取引に焦点を当てた法律として運用されていく予定です。
企業側から見ると、「新しい法律が増える」というよりも、「中小・零細企業やフリーランスを含めた取引の基本ルールが整理される」と捉えていただくとイメージしやすいかと思います。
下請法が大きく改正され、名称も変わる背景
従来の下請法は、日本の高度成長期から続く、多重下請け構造を前提に作られてきました。そのため、製造業や建設業といった、いわゆるモノづくりの取引には馴染みがありますが、サービスやデジタルコンテンツの委託には、必ずしもフィットしていない面がありました。
一方、インターネットの普及に伴い、個人がスキルを活かして働くフリーランスや、小規模なクリエイティブチームが増加しています。ホームページ制作の現場では、デザイナー、ライター、カメラマン、エンジニアなど、多様な専門職が関わり、企業と個人・小規模事業者の取引が当たり前になっています。
しかし、発注側の優越的な立場を背景に、
- 合意していない追加作業を無償で求める
- 支払いサイトが極端に長い
- 明確な理由のない値下げを強く迫る
といった事例も少なくありませんでした。こうした実態を踏まえ、「時代に合っていない部分を改め、デジタル時代の取引を見据えたルールにしよう」という方向性で、下請法の見直し・名称変更が進められています。
特にWEB業界では、口頭やチャットでの曖昧な指示がトラブルの火種になることが多く、今回の改正は、そうした不明瞭な商習慣を見直すきっかけになると考えられます。
フリーランスも保護対象になる大きな変化
今回の大きな流れとして、「フリーランスや小規模事業者も、法律で守られる対象として明確に位置付けていく」という動きがあります。
すでに2024年11月には、フリーランスとの取引に焦点を当てた「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)」が施行され、以下のようなことなどが定められています。
- 取引条件を明記した書面(またはメール等)の交付義務
- 納品から60日以内のできるだけ短い期間での報酬支払い義務
- 不当なやり直しや著しく低い単価の押し付けの禁止
- 一定期間以上の継続的な契約を途中で打ち切る際の、原則30日前までの予告
- ハラスメント防止の体制整備
これに加えて、2026年1月1日から取適法が施行されることで、中小企業や個人事業主を含む「中小受託事業者」との取引全体に関するルールが、さらに整理・強化されていく流れです。
WEB担当者の周りにも、フリーランスのWebデザイナーやカメラマン、SEOライターなど、個人で活動しているパートナーがいらっしゃると思います。
今後は「個人の外注さんだから柔軟に対応してくれるだろう」という感覚ではなく、「法律によって一定の保護が与えられているビジネスパートナー」として、取引条件や支払い方法をていねいに扱うことが求められます。
委託する側が対応すべき法的義務の重要性
「うちは中小企業だから関係ない」「規模も予算も大きくないから大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、取適法やフリーランス新法は、まさに中小企業とフリーランスの取引も念頭に置いています。
委託する側(発注者)には、発注内容の明確化や支払期日の設定など、具体的な義務が課されており、違反した場合には行政による指導・勧告だけでなく、社名の公表といった措置が取られる可能性もあります。
発注者として特に意識しておきたいのは、「日々のメールやチャットでのやり取りも、法律上の取引条件を示す記録になりうる」という点です。
- 「なるべく早めで、デザインだけ先にお願い」
- 「金額はあとで相談しましょう」
といった曖昧な依頼は、今後は見直す必要があります。法律の条文を細かく記憶する必要はありませんが、
- どのような行為が問題とされるのか
- 最低限押さえるべきルールは何か
を理解しておくことは、自社とご自身を守るうえで、欠かせない基礎知識になっていきます。
取適法(中小受託取引適正化法)と下請法の違い|対象範囲と規制の強化
新しく始まる取適法は、従来の下請法と比べて何が変わるのか。まずはその全体像を整理しておくことが大切です。
| 比較項目 | 下請法(従来) | 取適法(2026年1月施行) |
|---|---|---|
| 法律の目的 | 親事業者による不公正な取引(支払遅延・買いたたき等)の防止 | 中小受託事業者(個人含む)の取引条件をより適正化し、公平な関係を構築する |
| 主な対象事業者の考え方 | 資本金規模による「親事業者」「下請事業者」の厳密な区分 | 資本金+従業員数を基準にしつつ、より幅広く中小事業者を保護 (フリーランスを含む) |
| 想定している主な業種・背景 | 製造業・建設業など重層的な下請け構造を想定 | デジタル・制作業務や個人委託など現代的な業務委託関係を想定 |
| フリーランスの位置づけ | 保護の対象外になるケースが多い | 保護を受けやすい (フリーランス新法とも連動) |
| 発注内容の書面化 | 書面交付義務あり (ただし対象範囲が限定的) | 原則すべての発注内容を書面または電磁的記録で明示する必要あり |
| 支払いサイト(期日) | 60日以内の規制あり | 「60日以内」かつ「できる限り短い期間」での支払い義務をより強調 |
| 禁止行為 (買いたたき・受領拒否など) | 既存の禁止行為を規定 | フリーランス新法の規制とも組み合わせ、禁止行為の実効性が強化される |
| 契約解除に関するルール | 明確な規定は限定的 | 継続契約の中途解除には「合理的な理由」や「30日前予告」(フリーランス新法)が必要 |
| 対象取引の範囲 | 限定的 (判定がわかりにくいとの指摘) | WEB制作・デザイン・記事制作・システム開発など、中小企業 × 個人の取引が対象になりやすい |
| 現場への影響度 | 業種により影響の差が大きい | WEB制作やデジタル関連の発注業務では影響が大きく、実務変更が必要 |
この表のとおり、取適法では対象事業者が広がり、現代の働き方に即した形でルールが整理されています。
大まかに整理すると、以下のように理解するとよいでしょう。
- 従来の下請法 → 主に製造業など、特定の業種・取引形態に焦点が当たっていた
- 改正後の取適法 → 中小企業や個人事業主を含む、より幅広い「中小受託事業者」との取引を対象にし、現代の働き方に合わせてルールを整理
ここからは、WEB担当者の実務に特に影響が出やすい「適用範囲」「資本金・従業員数の考え方」「違反時のリスク」について見ていきます。
取適法で変わる適用範囲と資本金・従業員数の考え方
従来の下請法では、「親事業者(発注側)」と「下請事業者(受注側)」の関係が主に資本金の額によって決められていました。
- 資本金3億円超の会社が、資本金3億円以下の会社に発注する場合
- 資本金1,000万円超の会社が、資本金1,000万円以下の事業者に発注する場合
といった具合に、細かい線引きがありました。そのため、実務担当者としては「このパートナーとの案件は、下請法の対象なのかどうか」を即座に判断しづらいという課題がありました。
取適法では、この資本金だけの考え方を見直し、「資本金」と「常時使用する従業員数」の両方を基準にしながら、より広く中小事業者を保護する仕組みに変わっていきます。
詳細な線引きは公的な資料での確認が必要ですが、実務的には、以下のような感覚を持っておくことが大切です。
- 相手がフリーランスや小規模な制作会社の場合は、法律の対象になる可能性が高い
- 「大企業だけの話」と考えるのではなく、自社のような中小企業も関係してくる
すべての取引が一律で対象になるわけではありませんが、「外部の小規模なパートナーには、原則として丁寧な条件提示と支払いを行う」というスタンスを取っておけば、結果として法令遵守に近づいていきます。
違反した場合のリスクと企業の責任
下請法の時代から、買いたたきや支払遅延などに対しては、行政による指導・勧告の仕組みが存在していました。
取適法やフリーランス新法では、こうした監視・是正の体制が、フリーランスを含む中小事業者にもより一層届きやすいよう整えられていきます。
また、近年はSNSなどで情報が広まりやすく、「法的な処分」だけでなく「ブランドイメージ」という観点からのリスクも見過ごせません。
- 不当な条件を押し付けている
- 支払いが遅れがちで信頼できない
といった評判が広がれば、優秀なパートナーが集まりにくくなり、結果として自社のWEB施策そのものが弱くなってしまうおそれがあります。
経営層が「コンプライアンス重視」を掲げていても、現場レベルの振る舞いが伴っていなければ意味がありません。
納期直前に無理な修正を繰り返し要求したり、支払いの手続きを後回しにしてしまったりすると、それ自体が企業としてのリスクとなります。
取適法やフリーランス新法は、「知らなかった」では済まされない時代のルールです。だからこそ、発注側の一人ひとりが基本的な内容を知っておくことが、企業を守ることに繋がります。
業務委託契約において見直すべきポイント
取適法の施行に合わせて、現在使用している「業務委託契約書」や「発注書」のひな形を、この機会に見直しておくことをおすすめします。
これまでの契約書では、
- 著作権の帰属
- 機密保持(守秘義務)
などは比較的しっかり書かれている一方で、
- 支払期日の具体性
- 検収の方法と期限
- 無償修正の範囲
- キャンセル時の取り扱い
といった、取引条件の肝心な部分が曖昧なままになっているケースも少なくありません。
例えば、「検収完了後の翌月末払い」とだけ書かれている場合、検収のタイミングを明確にしないと、事実上の支払遅延につながりかねません。また、「修正は都度相談」といった記載では、どこからが有償対応なのか、発注側と受注側で認識がずれやすくなります。
見直しのポイント
- 発注内容・納期・報酬の明確化
- 修正の範囲や回数、追加費用が発生する条件
- キャンセル時の費用精算ルール
- 支払サイトが60日以内に収まっているか
WEB制作では仕様変更が起きやすいため、「なんとなくの話し合い」で済ませず、必要に応じて契約書や発注書を更新し、記録に残す仕組みを作っていくことが重要です。
企業が必ず押さえるべき取適法の5つの重要ポイント
ここからは、WEB担当者が日々の発注業務で特に意識しておくべき点を、5つの観点から整理していきます。これらは“マナー”というより、法律やガイドラインに基づいた「守るべきライン」と考えていただくとよいでしょう。
- 発注内容を、口頭ではなく書面(メール等)で残すこと
- 納品から60日以内のできるだけ短い期日で、支払いを行うこと
- 買いたたきや、不当な無償修正を行わないこと
- 正当な理由なく成果物の受領を拒否しないこと
- 検収を意図的に遅らせて、支払いを先延ばしにしないこと
それぞれ、WEB制作の現場で起こりがちな例と合わせて見ていきましょう。
発注書面の交付義務と60日以内の支払いルール
まず最初のポイントは、「発注内容を必ず書面に残すこと」と「60日以内に支払期日を設定すること」です。
- 「とりあえずトップページのデザインだけ進めておいて」
- 「金額や締め切りは、あとで相談しましょう」
今後は上記のような口頭ベースの依頼は避ける必要があります。メールやチャットなどの“電磁的記録”も書面の一種として認められますが、その場合も、内容が後から確認できる形で残っていることが前提となります。
最低限、以下のような項目は記録として残しておきたいところです。
- 何を作ってもらうのか(業務内容)
- いつまでに必要なのか(納期)
- いくらで依頼するのか(報酬額)
また、支払いについては、「成果物を受け取った日から60日以内」の、できるだけ短い期間で支払期日を設定することが求められます。 実務では「月末締め・翌々月末払い」といったサイトが用いられることがありますが、納品のタイミングによっては60日を超えてしまう可能性があり、違反リスクが高くなると考えられます。
経理部門とも連携しながら、自社の支払いサイトが法律の趣旨に沿っているかどうかを、早めに確認しておくと安心です。
買いたたきや不当なやり直しの禁止事項
二つ目のポイントは、「買いたたき」と「不当なやり直し」の禁止です。
買いたたきとは、本来支払うべき対価よりも著しく低い単価を、一方的な立場を利用して押し付ける行為を指します。
- 「今回は予算が厳しいので、半額でやってくれませんか。次の案件で調整しますから」
- 「他社はもっと安くやってくれると言っている」
といった言い方で、断りにくい状況を作ってしまうと、買いたたきと受け取られるリスクがあります。価格交渉自体は問題ありませんが、相場や過去案件との整合性を意識しながら、あくまで“対等な交渉”として行うことが大切です。
不当なやり直しについても注意が必要です。WEBデザインや記事制作では修正がつきものですが、
- 事前に合意した仕様は満たしている
- 品質上の重大な問題もない
にもかかわらず、
- 「なんとなく雰囲気が違うから、全部作り直してほしい」
- 「社長の好みじゃなかったので、ゼロからやり直してほしい」
といった理由で、大幅な無償修正を繰り返し求めることは認められません。発注側の都合による修正や方針変更であれば、原則として追加費用の支払いが必要になります。
これを防ぐためには、発注の段階でイメージやゴールをできるだけ具体的に共有し、修正回数や範囲についても合意しておくことがポイントです。
成果物の受領拒否と検収遅れへの対策
三つ目と四つ目のポイントは、「受領拒否」と「検収遅れ」です。
受領拒否とは、依頼した成果物が問題なく納品されているにもかかわらず、「不要になったから」「社内事情でプロジェクトが止まったから」といった理由だけで受け取りを拒む行為を指します。相手に明らかな瑕疵がある場合を除き、発注した以上は受け取り、代金を支払う義務があります。
また、WEB担当者が特に意識したいのが検収遅れです。納品連絡が来ているにもかかわらず、
- 多忙を理由に確認を先延ばしにしてしまう
- 「承認待ち」の状態が長期間続いてしまう
といったことが続くと、実質的な支払遅延と見なされる可能性があります。検収のフローが複数部署にまたがる場合は、どこで止まりやすいのかを洗い出し、スムーズに進むよう社内ルールを整理しておくことが重要です。
どうしても時間がかかる場合は、その旨をパートナー側に率直に伝えたうえで、支払期日への影響が出ないよう工夫しておくと、お互いの信頼にもつながります。
発注側が注意すべきフリーランス保護の改善点
取適法やフリーランス新法では、単にお金の話だけでなく、働く環境や人間関係の面にも踏み込んだルールが整えられつつあります。フリーランスは企業の内部にはいないため、どうしても立場が弱くなりやすく、ハラスメントや一方的な契約解除の影響を受けやすいからです。
ここでは、WEB担当者の立場から、特に意識しておきたいポイントを整理します。
急な仕様変更やキャンセル時の費用補償
ホームページ制作のプロジェクトでは、要件定義が変わることは珍しくありません。
- 「やはりこの機能も必要になった」
- 「ページ構成を大きく変更したい」
といった変更は、より良いサイトを目指すうえで必要なことも多いでしょう。ただし、フリーランスや小規模事業者が相手の場合、その変更によってスケジュールや作業量が大きく変わり、収入にも直結します。
法律やガイドラインでは、発注側の都合による内容変更やキャンセルによって、受注者に損失が生じた場合には、その分の補償を行うことが求められます。
- プロジェクトが途中で中止になった
- すでに確保してもらっていた作業時間が不要になった
といったケースでも、「完成していないから0円」で済ませるのではなく、それまでの作業分や拘束してもらった時間に対する対価を支払う必要があります。
そのためには、契約書の段階で、
- キャンセルになった場合の精算方法
- 大きな仕様変更が生じた際の追加見積もりのルール
を決めておくことが大切です。WEB担当者は、社内の要望変更を外部パートナーにそのまま伝えるだけでなく、「それがコストにも影響する」という事実を社内に理解してもらう役割も担っています。
契約解除の「合理的な理由」とハラスメント防止
継続的な記事制作や保守運用など、半年以上にわたる業務委託では、途中で契約を見直す場面も出てくるかもしれません。フリーランス新法では、一定期間以上の継続契約を一方的に打ち切る場合、原則として30日前までの予告や、合理的な理由の提示が求められるとされています。
- 単に「なんとなく合わない気がする」
- 特に問題はないがコストだけを理由に、急に切り替える
といった対応は、相手の生活や事業に直接影響するため、慎重な判断が必要です。品質や納期の問題など、契約上の合理的な理由がある場合には、その内容を伝えたうえで協議し、できるだけ納得感のある形で見直しを進めるのが望ましいでしょう。
また、「ハラスメント防止」も重要なテーマです。相手が自社の社員ではないからといって、暴言や威圧的な態度、深夜・休日の連絡強要などが許されるわけではありません。
- 「仕事を出してやっている側」という意識を捨てる
- 「お互いにビジネスパートナー」という前提で接する
この意識を社内で共有しておくことが、結果として良い仕事にもつながります。
トラブルを未然に防ぐコミュニケーション
法律や制度の話はどうしても堅く感じられますが、根本にあるのは「コミュニケーションの質」です。多くのトラブルは、悪意ではなく「認識のズレ」から生じます。
取適法やフリーランス新法に対応していくうえでも、以下のような基本が重要になります。
- 言った・言わないを避けるために、やり取りを記録に残す
- 相手の状況や立場を想像しながら、無理のないスケジュールで進める
- 納期の相談をする際には、「このスケジュールで無理はありませんか?」と一言添える
- 打ち合わせ後には、簡単な議事録を共有して認識を合わせる
- 修正依頼では、「ここをこう変えたい理由」も合わせて伝える
こうした積み重ねが、お互いが気持ちよく仕事を進められる土台になり、最終的にはホームページの成果にもつながっていきます。
トラブルを防ぐための取適法対応チェックリスト
最後に、2026年1月1日の施行に向けて、実務にすぐ活かせるチェックリストを用意しました。 法律の専門家でなくても、この項目をひと通り見直すだけで、コンプライアンス違反のリスクを大きく下げることができます。
契約書と発注フローの再確認項目
まずは、ルールや書式の観点から、自社の体制を確認してみましょう。
- 依頼内容の「書面化」を徹底しているか
口頭発注を避け、必ずメールや発注書で内容・金額・納期を残す運用になっていますか? - 納期・支払日を契約書に明記しているか
「納品後60日以内」の支払いが守れるよう、支払いサイトを設定できていますか? - 無料修正の回数・範囲を設定しているか
「修正は○回まで」「仕様変更は別途見積もり」など、線引きが明文化されていますか? - 作業途中のキャンセル料を事前に明確化しているか
プロジェクト中止の際に、どの段階でいくら支払うのか、ルールがありますか? - 単価が低すぎないか&値下げ強要がないかチェックしているか
過去の案件や相場と比べて、不自然に低い単価を押し付けていませんか?
これらを整理しておくことで、WEB担当者自身が迷わず発注できるようになり、パートナーからの信頼も高まりやすくなります。
信頼される企業になるための社内体制づくり
次に、組織としての体制面を見直してみましょう。WEB担当者一人の努力だけでは限界があります。
発注担当者向けの社内説明・研修
取適法やフリーランス新法の基本的な内容を共有し、「何が問題行為になるのか」を共通認識にしておきましょう。
相談窓口の明確化
パートナーからの問い合わせや、現場での判断に迷うケースを相談できる窓口(法務、総務など)を決めておくと安心です。
パートナー台帳の整備
誰に、どのような条件で依頼しているのかを一覧できるようにし、条件や単価を定期的に見直せるようにしておくと、買いたたきの防止にも役立ちます。
法令順守は、コストというより「将来の投資」です。 「発注条件が明確で働きやすい会社」として認知されることで、優秀なクリエイターやホームページ制作会社が自然と集まりやすくなり、結果として自社のWEB戦略も強化されていきます。
正しい知識でホームページ制作の発注を行うために
2026年1月の取適法施行は、ホームページ制作やコンテンツ制作の発注業務における大きな転換点になります。
「ルールが増えて面倒になった」と捉えるのではなく、 「取引条件をお互いにきちんと確認して、トラブルを減らすチャンス」と捉えていただくと、前向きに取り組みやすくなるはずです。
法律やガイドラインの詳細は、今後も見直される可能性があります。定期的に、官公庁のホームページなどを確認し、最新の情報にアップデートしておくことも大切です。
この記事でご紹介したポイントを参考にしながら、外部パートナーとの関係をより良いものに育てていってください。 誠実な発注姿勢は、最終的に自社のホームページの品質や成果となって返ってくるはずです。
まずは以下の2点を意識するだけでも、大きな一歩になります。
- 口頭発注をやめる
- 納品から60日以内で支払いできる体制を整える
次のステップとして、「現在お使いの業務委託契約書や発注書のひな形を、この記事のチェックリストと照らし合わせて確認してみる」ことをおすすめします。
もし不足している項目があれば、法務担当者や顧問専門家に相談する良いきっかけになるでしょう。
参考
より詳しい内容や最新情報については、以下の公的な情報源もあわせてご確認ください。
政府広報オンライン「フリーランスとして安心して働くために」
https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9983.html
中小企業庁 取引適正化・フリーランス関連情報
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
取適法特設ページ | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025
(最新情報は各サイトで随時更新されますので、定期的な確認をおすすめします。)
取適法以外のホームページ制作・運用の際に覚えておきたい法律の知識に関して、以下記事にまとめておりますのでご参照ください。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。