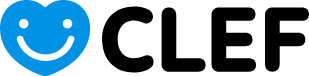AIを使ったホームページ制作前の競合調査|効果的な分析手順と成功のポイント
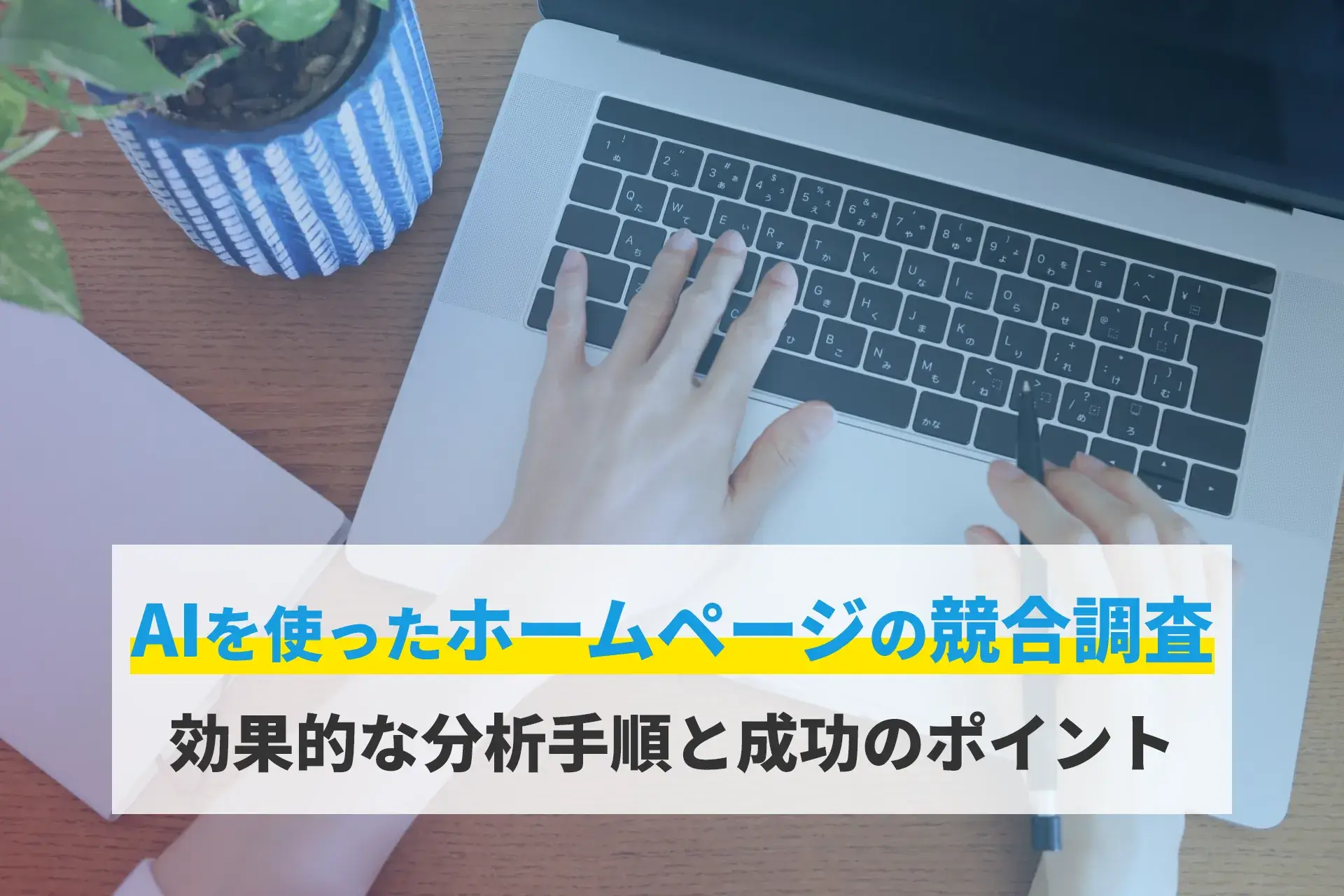
(監修:株式会社クレフ マーケティングチーム)
ホームページを新しく作るときやリニューアルを検討する際には、まず「競合調査」が欠かせません。市場でどんな企業が競い合い、どのような情報を発信し、ユーザーは何を基準に比較しているのか。こうした外部環境を把握することで、制作の方向性がブレず、競合と似た仕上がりになってしまうリスクも避けられます。
実際、競合を見ずに制作を進めた結果「気づけばよく似たホームページになっていた」という例は珍しくありません。そのため、初期段階で競合の特徴を整理し、自社の立ち位置を明確にすることが重要です。
しかし、競合調査は非常に手間がかかります。複数のホームページを読み込み、内容を比較し、ポイントごとに整理するだけでも半日以上かかることもあります。忙しい経営者や担当者にとって、十分な時間を割くのは簡単ではありません。
そこで注目されているのが「AI」を活用した競合調査です。AIなら大量の情報を短時間で整理し、人間では気づきにくい比較ポイントも抽出してくれます。主観に左右されず、フラットに分析してくれる点も大きな強みです。
本記事では、AIを使った競合調査の具体的な手順から、役立つツール、そして効果的なAIへの指示方法までをわかりやすく解説します。制作会社に依頼する前の準備として、ぜひ参考にしてください。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
目次
1. ホームページ競合調査にAIを使うべき3つの理由
競合調査にAIを取り入れる企業が増えている理由は明確です。単に作業が楽になるだけでなく、「人だけでは気づけない情報」が見えてくるようになるためです。ここでは主なメリットを3つの視点から解説します。
1-1:情報整理のスピードが大幅に向上する
競合ホームページの情報は膨大です。各社のサイトには、企業概要・サービス紹介・料金プラン・実績・コラム記事・採用情報など、多くのページが用意されている場合がほとんどです。
これらをすべて読み込み、特徴を手作業でまとめるとなると、大きな負担になります。しかも、読み進めるうちに情報が混在したり、どの会社のどこが強かったのか分からなくなることも珍しくありません。
AIは、この「読む」「整理する」「比較する」といった作業を非常に得意とします。人間の何倍ものスピードで文章を処理し、要点を正確にまとめてくれます。
さらに、AIは「抜け漏れなくまとめる」点でも優れています。人間はどうしても主観が入って大切な箇所を見逃してしまうことがありますが、AIはテキスト全体を均等に読み込み、客観的に抽出してくれます。
例えば、以下のような指示を出すだけでOKです。
- A社とB社の違いを、サービス内容・料金・サポート体制の3点でまとめてください
- このページの要点を200字以内で要約してください
短時間で情報を整理できるため、制作前の調査にかける時間を大幅に削減できます。
さらに補足すると、AIは単なる要約だけでなく「解釈」も行ってくれます。例えば、文章の流れから「ターゲット層」「どんな悩みに応えようとしているのか」といった隠れた意図も読み取ることができます。
このように、AIに情報整理を任せることで、人間は「方向性をどう決めるか」という本質的な判断に集中できるようになります。
1-2:主観や先入観に左右されず、客観的に分析できる
人には必ず「主観」があります。経験や価値観から「イメージ」を作り出してしまい、そのイメージが判断に影響します。
- この会社は昔から知っているから強くないだろう
- このデザインは自分の好みではないから参考外でいい
- この文章は読みづらいと感じるから、うちは別の方向で良いだろう
このような、小さな思い込みが分析に影響することがあります。
一方AIは、好みや感情を持っていません。与えられた情報をそのまま読み取り、内容を定量的に判断し、文章として整理します。
- どの言葉が多く使われているか(頻度分析)
- どんなテーマに重きを置いているか
- どのページに力を入れているか
- 何を強みにしているか
- どんなユーザー像を想定しているか
上記のように情報を、フラットに抽出してくれます。
「主観に左右されない情報」は、社内の合意形成にも非常に役立ちます。
「AIの分析としてこう出ています」という事実ベースの材料があれば、 「好き嫌い」「思い込み」ではなく、冷静かつ客観的な議論ができるようになります。
1-3:見た目だけでなく、SEO構造や内部設計まで読み取れる
競合サイトを見たとき、どうしても最初に注目しがちなのはデザインや写真、色使いなどの見た目です。しかし、ホームページで成果を出すには、それ以上に重要な「内部構造」を理解する必要があります。
AIは次のような構造的な情報の分析も得意です。
- 見出し(H1〜H3)の構成
- キーワードの使い方
- 記事全体の流れ
- 悩みへの回答がどこにあるか
- セールスポイントの優先順位
- ページ同士のつながり方
分析を進めるうちに、「この企業は初心者向けの安心感をメイン軸にしている」 「このホームページは価格の安さよりも信頼性を重視している」といった傾向が見えてくることもあります。
こうした内部分析は、人の目だけで行うと非常に時間がかかりますが、AIなら短時間で整理可能です。
2. 初心者でも扱いやすい競合調査向けAIツール
AIと聞くと「難しそう」「特別な知識が必要なのでは」と不安に思われる方もいますが、現在は誰でも使える対話型のAIツールが主流です。
ここでは、競合調査でも特に使いやすい3つのツールをご紹介します。
2-1:会話形式で使える「ChatGPT」
皆さんご存知のChatGPTは、自然な会話形式で操作ができるAIです。質問を入力するだけで回答が返ってくるため、難しい操作は不要です。
使い始めるハードルは非常に低く、例えば次のような質問をするだけで競合分析が進みます。
- 「この文章をわかりやすく200字でまとめてください」
- 「A社とB社を、サービス・料金・サポートの観点で比較してください」
- 「このページから想定されるターゲット層を教えてください」
無料版でも十分活用できますが、一部の有料プランでは次のような機能も利用できます。
- URLを貼るだけでページを読み込んで分析
- 表形式での比較
- 長文の高度な要約
- キーワード分析の精度向上
制作会社に依頼する前の準備として、自分の頭の中を整理するツールとしても非常に重宝します。
2-2:検索×整理が強い「Perplexity」
Perplexityは、インターネット検索とAI分析を組み合わせたような便利なツールです。
最大の特徴は、根拠となるURLを提示してくれることです。
AIの回答だけでなく「どのページを参考にして回答したか」も示してくれるため、裏付けが取りやすく、信頼性の高い調査ができます。
業界トレンドの把握や最新ニュースの収集にも向いており、
- 業界の最新動向
- サービスの比較表の作成
- 競合企業のニュースまとめ
- 市場規模の傾向調査
など幅広く活用できます。登録不要で使えるため、最初に試しやすいツールのひとつです。
2-3:専用ツールでの深堀り分析も可能
より具体的な数値データや市場情報が必要な場合には、専用の分析ツールが有効です。
- Semrush
- Ahrefs
- SimilarWeb
などが代表的で、検索流入の推定量や競合サイトの広告出稿状況、キーワード分析など、ホームページの裏側の戦略が見えてきます。
こうしたツールは費用がかかるため、最初から導入するよりも、必要なタイミングで制作会社にスポット依頼する方法が現実的です。
3. AIを使った競合調査の実践ステップ
ここからは、AIを使って競合調査を実施する具体的な手順を紹介します。
3-1:調査対象の競合サイトをリストアップする
まず、どの企業を対象に分析するかを決めます。ここが曖昧なまま進めると、調査の方向性もブレてしまいます。
以下の3つの視点で競合を選ぶと、偏りのない分析ができます。
- 直接競合 商圏・サービス内容が近く、実際に顧客を取り合う相手
- 検索競合 自社が狙いたいキーワードで上位表示されている企業
- 参考サイト 業種は異なるが、デザイン・構成・雰囲気が自社の理想に近いサイト
特に重要なのは「検索競合」です。実際の市場では、ユーザーは業種や企業の規模に関係なく、検索結果に出てきたものを比較して判断します。
そのため、同業ではなくても検索上位にいる企業は立派な“競合”です。
選んだ企業のURLをリスト化し、AIに読み込ませる準備をします。 トップページのキャッチコピーや「選ばれる理由」「サービス説明」などのテキストをコピーしておくと、AIの分析精度も高まります。
3-2:ターゲットや訴求ポイントを比較する
AIに分析させる際、最も大切なのは「質問を明確にすること」です。
- 誰に向けて書かれているか(ターゲット層)
- 何を強みとして打ち出しているか(USP)
- どのような問題を解決しようとしているか
- デザインから受ける印象はどうか
- どの検索キーワードを意識しているか
こうした観点を事前に指定したうえで、 「表形式で比較してください」と依頼すれば、読みやすい分析結果が得られます。
社内会議で共有する資料としても、そのまま活用できるレベルです。
3-3:自社が取るべき勝ち筋を導き出す
競合調査の目的は、単に情報を集めることではありません。その先にある「自社が勝てるポイント」を見つけることがゴールです。
AIはこの壁打ちにも最適です。
例えば次のように聞くと、AIは複数の視点を提示してくれます。
競合A社は価格を重視し、B社は品質を訴求しています。 当社はサポート体制を強みにしていますが、この強みを活かしてどのように差別化すべきでしょうか。
こうした質問に対して、AIは次のような角度の違う提案を返してくれます。
- サポート体制の実例を具体的に掲載する
- 担当者紹介ページで「人の見える安心感」を強調
- 過去のサポート対応事例をストーリー形式で掲載
このように、AIは多角的な視点での提案を得意とするため、制作会社との打ち合わせでも大いに役立ちます。
4. 質の高い回答を引き出すためのAIへの指示(プロンプト)
AIは非常に優秀ですが、指示の出し方ひとつで回答の質が大きく変わる「指示待ち型のツール」です。 ここでは、すぐに実践できる3つのコツをご紹介します。
4-1:まず「役割」を与える
AIに「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与えるだけで、回答の深さが変わります。
- あなたはWebマーケティング歴20年のコンサルタントです
- あなたはITが苦手な50代ユーザーです。率直にどう感じるか教えてください
このように、求める視点に合わせて役割を設定することで、より具体的で実践的な回答が得られます。
4-2:出力形式を指定する
長文で返されると読みづらい場合があります。そうしたときには、出力形式を明確に指定しましょう。
- 表形式
- 箇条書き
- 要点だけ3つ
- 小学生でもわかる説明
制作会社に共有するときにも、形式が整っている方が便利です。
4-3:すぐ使える競合分析プロンプト例
以下のテンプレートは実際の業務でそのまま使える実践的な内容です。
あなたは経験豊富なWebマーケターです。
これから入力する競合サイト3社の情報を読み込み、以下の観点で比較表を作成してください。
【分析項目】
- ターゲット層
- 強み(USP)
- 訴求ポイント
- デザインの印象
- 検索キーワードの意図
最後に、自社が差別化するためのアイデアを3つ提案してください。
5. AI分析を活用する際の注意点
AIは非常に便利で力強いツールですが、注意して扱う必要があります。
5-1:AIの回答は「参考情報」として扱う
AIは文章生成が得意ですが、まれに事実と異なる情報(ハルシネーション)を返すことがあります。特に次のような情報は必ず実際のサイトで確認しましょう。
- 料金
- 営業エリア
- 実績数
- キャンペーン内容
AIの回答はあくまで「整理されたヒント」と捉え、人間の最終確認を必ず行うことが大切です。
5-2:ユーザーの感情までは完全に理解できない
AIは論理的な分析が得意ですが、「雰囲気」「安心感」「信頼感」などの感覚的な要素は苦手です。
- 綺麗だが冷たく感じるデザイン
- 情報は充実しているが、人の温度を感じない文章
- 写真は良いが、ターゲット層と合っていない印象
こうした人の感覚は、制作前の判断において非常に重要です。AIの分析と、人の感覚を併せて判断することが求められます。
5-3:分析結果を制作物に落とし込むには、プロの技術が必要
AIは分析や比較、アイデアの整理は得意ですが、「分析結果を形にする(デザイン・構成・文章にする)」作業は、人間の専門性が不可欠です。
- どのような構成にするか
- どこに強みを配置するか
- デザインの方向性をどうまとめるか
こうした判断は、制作会社の経験に基づくものが大切です。
AIによる分析で方向性が明確になっているほど、制作会社も提案がしやすくなります。
AIを活用した競合調査のまとめ
競合調査は、ホームページ制作の成功に欠かせない重要なステップです。しかし、手作業だけで行うには時間も労力も必要で、見落としも起こりがちです。
AIを活用すれば、短時間で大量の情報が整理でき、主観に左右されない客観的な分析が可能になります。また、AIが抽出した要点をもとに制作会社と連携することで、より目的に合ったホームページ制作が実現しやすくなります。
AIはあくまで補助ツールですが、うまく使えば競合調査の質を大きく引き上げ、制作プロセス全体をスムーズにしてくれます。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。