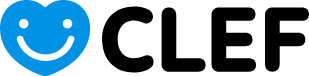AIO/LLMO/GEOとは?AI時代の必須対策とSEOとの違い

(監修:株式会社クレフ マーケティングチーム)
AIが検索結果の一番上で答えを示す「AI検索」が広がる中、これまでのSEOだけでは十分に情報が届かない時代が近づいています。そこで注目されているのが、AIO・LLMO・GEOという新しい考え方です。
これらは、AIが答えを作る際に「どの会社の情報を参考にするか」を左右する取り組みで、今後の集客に大きく関わります。
本記事では、AIO・LLMO・GEOの基本的な意味から、SEOとの違い、AIに選ばれるためのコンテンツづくり、中小企業がまず取り組むべき実践策を解説します。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
目次
AIO/LLMO/GEOとは?AI時代の新たなWEB戦略
最近、「AIO」や「LLMO」、「GEO」といった新しい言葉を耳にする機会が増えてきました。どれも、ChatGPTのような対話型AIや、Google検索の「AIによる概要表示」など、AIが直接答えを返す時代に対応するための考え方です。
これまでは「検索結果で上位に表示されること(SEO)」が中心でしたが、これからは「AIが答えを作るときに、どの会社の情報を参考にするか」が重要になってきます。 この記事では、こうしたAI時代の最適化を総称して「AIO/LLMO/GEO対策」と呼びながら、その基本的な意味と、従来のSEOとの違いを分かりやすく整理していきます。
AIO (AI最適化) とは?
AIOは本来さまざまな意味で使われる用語ですが、本記事では便宜的に「AI Optimization(AI向けの最適化)」の略として扱います。あわせて、近い概念として「Answer Engine Optimization(AEO)」と呼ばれる考え方もあり、こちらは「答えを返すエンジン」に最適化する、という発想です。
従来のSEO(検索エンジン最適化)は、GoogleやYahoo!といった検索エンジンが対象でした。ユーザーがキーワードを入力し、検索結果に表示されたサイトの中から、自社サイトをクリックしてもらうことがゴールでした。
一方で、AIOが意識するのは「回答エンジン」や「AIそのもの」です。
- Googleの「AI Overviews(AIによる概要表示)」
- ChatGPT
- MicrosoftのCopilot
上記のようなユーザーの質問に対してAIが直接「答え」を返す仕組みです。
AIO対策の狙いは、これらのAIが答えを作るときに、自社サイトの情報を信頼できる材料のひとつとして参照してもらうことです。AIの回答文の中で、自社名や自社サービスが引用されたり、出典として紹介されたりすれば、ユーザーが検索結果をクリックしなくても、会社の存在を知ってもらえる可能性が高まります。これがAIOの基本的な考え方です。
LLMO (大規模言語モデル最適化) とは?
LLMOは「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略です。こちらもAIOと近い考え方ですが、「何を相手にしているか」が少し違います。
ChatGPTやGoogleのGeminiなどの対話型AIは、「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれる仕組みを使って動いています。LLMは、インターネット上の膨大な文章を学習し、その結果をもとに自然な文章を生成します。
LLMOとは、簡単に言えば、
「生成AIが回答を作るときに、自社サイトの情報を理解しやすくし、回答の候補に入れてもらうための工夫」
と考えると分かりやすいかもしれません。
AIOが「AIが返す答え(アウトプット)の中にどう入るか」に着目するのに対し、LLMOは「AIが情報を読み取り、理解するとき(インプット・理解プロセス)」に焦点を当てた考え方です。 どちらにしても、目的は生成AIにとって使いやすい情報に整えることであり、AIO/LLMOはセットで語られることが多くなっています。
GEO (生成エンジン最適化) とは?
GEOは「Generative Engine Optimization(生成エンジン最適化)」の略です。研究分野では新しい概念として紹介されており、実務ではAIOやAEO、LLMOと近い意味合いで使われることも多い言葉です。
ここでいう「生成エンジン」とは、文字通り新しいコンテンツを生成するAIを指します。
- AIが複数サイトの情報をまとめて回答を作る
- 長い記事を短く要約する
- 文章や画像を自動生成する
といった機能の裏側で働いている仕組みです。
GEO対策とは、この「生成エンジン」が回答や要約を作る際に、自社の情報をきちんと拾い、正しく使ってもらうための最適化全般を指します。
承知しました。
「AIO/LLMO/GEOとは?AI時代の新たなWEB戦略」**このセクション内で説明している内容“だけ”**を整理し、表にまとめました。
(本文の表現・ニュアンスを崩さず、要点だけを比較できる形です。)
AIO・LLMO・GEO(この章で説明した内容のまとめ)
| 項目 | AIO (AI最適化) | LLMO (大規模言語モデル最適化) | GEO (生成エンジン最適化) |
|---|---|---|---|
| 対象 | AIの「回答生成」全般(AI Overviews・ChatGPT・Copilotなど) | ChatGPTやGeminiなど、文章を生成する「大規模言語モデル(LLM)」 | 回答や要約を生成するAI全般(生成エンジン) |
| 考え方の中心 | AIが答えを作る際に「自社の情報を参照してもらう」 | AIが自社情報を読み込んだときに「正しく理解・学習してもらう」 | AIが回答を作る“生成プロセス”で「自社情報を使ってもらう」 |
| 特徴 | ・AI版の“情報源最適化”・回答文に引用されることを狙う | ・AIの理解プロセス(インプット)に着目・AIO/GEOの土台となる考え方 | ・AIO/LLMOとほぼ同じ文脈で使われることも多い・AI検索全般の最適化 |
| ポイント | AIに“信頼できる情報源”として扱ってもらうことが重要 | AIに読み解きやすい内容・品質を高める | AIがまとめる回答の材料として拾われるようにする |
AIO、LLMO、GEOは、提唱する人や文脈によって細かい定義が少しずつ異なりますが、押さえておくべきポイントは共通です。
「検索エンジン(Google)だけでなく、AIという新しい情報提供者にも、自社の情報を分かりやすく伝え、選ばれる存在になること」
この記事では、この3つをまとめて「AIO/LLMO/GEO対策」と呼びながら、考え方と具体策を解説していきます。
AIO・LLMO・GEOと従来のSEOは何が違うのか
AIO/LLMO/GEOという新しい概念が出てくると、「今まで頑張ってきたSEO対策は、もう意味がないのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げると、SEOは不要になるどころか、AIO/LLMO/GEO対策の土台として今後も重要です。
ここでは、従来のSEOとAIO/LLMO/GEOが「何を目指し」「どう評価されるのか」という違いと関係性を整理してみます。
目的の違い:検索順位(クリック) vs AIによる引用(回答)
従来のSEOにおいてのゴールは、とても分かりやすいものでした。
「特定のキーワードで検索されたときに自社サイトを検索結果の上位に表示させタイトルや説明文を見たユーザーにクリックしてもらう」
つまり、「自社サイトへの訪問者を増やすこと」が最大の目的でした。
一方で、AIO/LLMO/GEOの主な目的は少し違います。 AIが生成する「答えそのもの」の中に、自社の情報が引用・参照されることがゴールになります。
たとえば、GoogleのAI Overviewsのように、検索結果の一番上にAIが要約した答えが大きく表示されるようになると、多くのユーザーは、その要約だけを読んで疑問が解決してしまいます。そうなると、従来の青いリンクをクリックしない(ゼロクリック検索)が増える可能性があります。
このような環境では、
検索結果で1位を取ること「だけ」を狙うという発想から、AIの答えの中に名前を出してもらい、認知や信用を高めるという発想が必要になります。 AIO/LLMO/GEO対策は、この「ゴールの変化」に対応する取り組みだと考えるとイメージしやすいでしょう。
評価基準の違い:アルゴリズム vs 文脈と信頼性
従来のSEO対策では、Googleの検索アルゴリズムにどう評価されるかが重要でした。
- 外部サイトからのリンクの質と量
- キーワードの配置
- ページの表示速度
- モバイル対応(スマートフォンでの見やすさ)
など、技術的な要素も含めて総合的に評価され、その結果として順位が決まります。
一方、AIO/LLMO/GEOを意識したとき、AIが見るポイントは少し変わります。 生成AIは、人間に近い形で文章の意味や文脈を理解しようとするため、以下のような「答えとしての完成度」を重視します。
- ユーザーの質問に対して
- どれだけ正確で
- 深く分かりやすく
- 誤解のない形で答えているか
さらに、
- その情報は誰が書いているのか
- どのような組織が運営しているのか
- 専門性や実績はあるのか
といった「情報源としての信頼性」も重要な評価材料になります。 キーワードをたくさん入れるだけのコンテンツや、小手先のテクニックだけで作られたページは、AI時代には評価されにくくなっていくと考えられます。
SEOは不要? AIO時代におけるSEOの重要性
では、「AIO/LLMO/GEOの時代になったから、SEOはもう古い」ということになるのかというと、答えは明確に「NO」です。
AIが回答を作るとき、多くの場合、その材料は既存のWebサイトに書かれている情報です。 そして、どのサイトの情報を参考にするかを判断する際には、
「すでに検索エンジンから高く評価されているか」 「信頼できるサイトとして扱われているか」
といった指標が使われていると考えられます(もちろん内部仕様は公表されていませんが、少なくとも無関係とは言いにくい部分です)。
つまり・・・
- 検索エンジンから「質の高いサイト」と認識されている
- 専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)が評価されている
こうしたサイトであることが、AIにとっても「参照しやすい情報源」になる可能性が高い、ということです。
逆に、SEO対策が不十分で、品質が低いと判断されているサイトは、そもそもAIに情報源としてあまり参照されない、という状況も考えられます。
AIO/LLMO/GEO対策をうまく機能させるためには、まず従来のSEOで「信頼できるサイト」と見なされることが出発点になります。 SEOは、AI時代における「次の一手」に進むためのスタートラインと言えるでしょう。
なぜ今AIO/LLMO/GEO対策が注目されるのか
ここまでで、AIO/LLMO/GEOという考え方とSEOとの関係性は、おおよそイメージしていただけたかと思います。
では、なぜ「今」これほどまでにAIO/LLMO/GEO対策が話題になっているのでしょうか。 その背景には、企業として無視できない3つの変化があります。
Google「AI Overviews」などAI検索の急速な普及
まず一つ目が、Google自身の動きです。 検索の世界で圧倒的なシェアを持つGoogleが、AI検索に大きく舵を切っています。
2024年5月、Googleはアメリカで、検索結果の最上部にAIによる回答を表示する「AI Overviews(AIによる概要)」を正式導入しました。ユーザーが少し複雑な質問をしたときでも、AIが複数のWebサイトから情報を集めて要約し、「ひとつの答え」として提示してくれる仕組みです。
このスタイルが日本でも広く使われるようになると、
- 画面の一番目立つ場所をAIの回答が占める
- 従来の青いリンクは、その下に押し出される
という状態になります。 多くのユーザーは、まずAIの回答を読み、それで足りればそのまま離脱してしまうかもしれません。
そうなると、たとえ従来のSEOで2位・3位を取っていても、「AIの回答の中で触れられていない」ページは、ユーザーの目に触れる機会が大きく減ってしまうおそれがあります。 これが、AIO/LLMO/GEO対策が「急がなければいけない」と言われる理由のひとつです。
ユーザーの情報収集行動の変化(検索から「対話」へ)
二つ目は、ユーザー(特に若い世代)の情報の集め方が変わってきている点です。
これまでは、「知りたいことをキーワードに分解し、検索窓に入力し出てきたサイトをいくつか開いて読み比べる」というのが一般的でした。
しかし、ChatGPTなどの対話型AIが登場したことで、
- 「〇〇について分かりやすく教えて」
- 「AIOとSEOの違いを、初心者向けに説明して」
- 「大阪でAIOに詳しい会社を探している」
といった形で、AIに直接話しかけるように質問を投げるスタイルが広がっています。
このとき、ユーザーが触れているのはWebサイトそのものではなく、「AIがまとめた回答」です。 言い換えると、ユーザーはAIとの対話の中で、あなたの会社を知るかどうかが決まるという状況になりつつあります。
- AIが「この質問なら、この会社の情報が役に立つ」と判断してくれるか
- そのために必要な情報が、自社サイト上に分かりやすく整理されているか
といった視点がこれまで以上に重要になってきます。 ここに、AIO/LLMO/GEO対策の必要性があります。
サイトへのトラフィック(流入)が減少するリスクへの備え
三つ目は、ビジネスの数字に直結する話です。
AI Overviewsや対話型AIが普及し、「ゼロクリック検索」が増えていくと、これまで検索から多くのアクセスを獲得していたサイトでも、ページの訪問者数(トラフィック)が減少するリスクがあります。
アクセスが減る → お問い合わせや資料請求などのコンバージョンが減る → 売上にも影響する
という流れになりかねません。
AIO/LLMO/GEO対策は、
- たとえサイト訪問者が減ったとしても
- AIの回答の中で自社が紹介されることで
- 認知や信用を維持・向上させていく
ための「守り」と「攻め」を兼ねた戦略です。「今まで通りのSEOだけ」に依存しないための備えとして、検討しておく価値があります。
AIに選ばれるために必要なコンテンツの条件
では、AIはどのようなコンテンツを「答えの材料」として選んでいるのでしょうか。 もちろん内部の仕組みはすべて公開されているわけではありませんが、これまでの情報から見えてきているポイントがあります。
ここでは、AIに選ばれやすいコンテンツの条件を3つに整理してご紹介します。
1.専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)の重要性
従来のSEOでも重要視されてきた考え方に「E-E-A-T」があります。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
の頭文字を取ったもので、「この情報は安心して信じてよいか」を判断するための指標です。
AIにとっても、このE-E-A-Tは非常に重要です。 AIが誤った情報を答えてしまうと、そのAI自体の信頼が下がります。そのため、もとになる情報源の信頼性をより慎重に見る必要があります。
具体的には、以下の点が重視されると考えられます。
- その道の専門家が書いているか
- その分野で実績のある企業が運営しているか
- 実体験に基づいた情報かどうか
- 会社情報・連絡先・運営者情報がはっきりしているか
AIに選ばれるコンテンツを作るには、「誰が」「どの立場で」「どのような経験に基づいて」 この情報を発信しているのかを、明確に示すことが欠かせません。 E-E-A-Tは、AIO/LLMO/GEO対策における前提条件と考えておくと良いでしょう。
2.AIが理解しやすい明確な「定義文」の記述
AIは、多くの文章を読み込み、そこから「これは〇〇の説明だ」「これは具体例だ」というように意味を読み取ります。
このとき、
- 「〇〇とは、△△のことです。」というような シンプルで分かりやすい定義文
- 結論を最初に伝え、その後に理由や事例を説明する 分かりやすい構成
があると、AIはそのページの内容を理解しやすくなります。
たとえば、「AIO/LLMO/GEOとは、AIが答えを作る際に、自社の情報を選んでもらうための新しいWeb戦略の総称です。」という一文があるだけでも、AIは「このページはAIO/LLMO/GEOを定義している」と認識しやすくなります。
人間の読者にとっても、
- 最初に「結論」「定義」を示す
- そのあとに「理由」「背景」「具体例」を続ける
という構成は理解しやすいものです。 AIと人、どちらにとっても親切な文章を意識することが、AIO/LLMO/GEO対策としても有効です。
3.読者の疑問に答える「FAQ形式」の活用
AIは、ユーザーの質問に対して最適な回答を探しにいきます。 その意味では、「質問(Q)と答え(A)がセットになった文章」は、AIにとって非常に扱いやすい素材です。
- 「AIO/LLMO/GEO対策にはどのくらい費用がかかりますか?」
- 「SEOとの違いは何ですか?」
- 「中小企業でも実践する価値はありますか?」
といった、実際にお客様から聞かれそうな質問を洗い出し、「よくあるご質問(FAQ)」としてページ内にまとめておくと、AIはそのQ&Aを理解しやすくなります。
これは、AI対策であると同時に、人間の読者にとっても読みやすいコンテンツです。 「自分の疑問がそのまま書かれていて、それに対する答えが載っている」という構成は、多くの方にとって親切な形式です。
中小企業が取り組むべき具体的なAIO/LLMO/GEO対策
ここまでの話を読んで、「理屈は分かったが、うちのような中小企業でそこまでできるのか?」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、AIO/LLMO/GEO対策の中には、大きな予算をかけなくても、中小企業だからこそ取り組みやすい施策が多くあります。ここでは、まず最初の一歩としておすすめしたい3つの対策をご紹介します。
著者情報・監修者情報を明記し「信頼できる情報源」を示す
最初に取り組みやすく、効果も大きいのが「著者情報・監修者情報の明記」です。
- この記事を書いた人は誰なのか
- 経験年数や役職、資格は何か
- どのような立場から話をしているのか
といった情報を、コラムの末尾やプロフィール欄に載せるだけでも、AIと人の両方に対して「信頼できる情報源」であることを伝えやすくなります。
以下のように記載します。
「この記事を書いた人:〇〇株式会社 代表取締役 山田太郎(業界歴20年)」
「この記事の監修者:中小企業診断士 佐藤花子(プロフィール・顔写真付き)」
匿名の文章よりも、責任を持って発信している専門家の文章の方が、信頼性が高いことは言うまでもありません。
しかし、昨今個人情報との兼ね合いもあり、本名を出すのが好ましくない場合もございます。
その場合は多少E-E-A-Tの効果は薄れますが、弊社のコラムのように、「監修:株式会社クレフ マーケティングチーム」と記載する方法もあります。
AIが読み解く「構造化データ(Schema.org)」の導入
少し専門的になりますが、AIO/LLMO/GEO対策として長期的な効果が期待できるのが「構造化データ(Schema.org)」の導入です。
構造化データとは、
「このテキストは会社名です」 「ここは住所です」 「これはFAQの質問文です」
といった情報を、検索エンジンやAIに分かりやすく伝えるための“ルール”のようなものです。
たとえば、「株式会社WEB大阪」という文字がページ内にあっても、そのままでは「社名」なのか「記事タイトル」なのか、機械には判断しにくい場合があります。そこで構造化データを使って、「これは組織(Organization)の名前です」と印をつけておくと、AIはより正確に理解しやすくなります。
もちろん、「100%誤解なく理解される」と言い切れるわけではありませんが、
- AIや検索エンジンに情報が伝わりやすくなる
- サイトの中身を「機械が読める形」で整理できる
という意味で、AIO/LLMO/GEO時代のサイト作りにおける基礎工事になります。 実装には専門知識が必要な場合もありますので、自社では難しい場合は、制作会社やエンジニアに相談しながら少しずつ進めていくと良いでしょう。
お客様の声や独自調査など「一次情報」の発信
AI時代に価値が下がりやすいのは、「どこにでも書いてあるような一般論」や、他社サイトの内容を寄せ集めただけのコンテンツです。そういった情報は、AI自身が短時間で生成できてしまうからです。
逆に言えば、AIが簡単には真似できない、以下のような一次情報こそが、AIから見て「価値の高いデータ」になります。
- 実際のお客様の声
- 自社で行ったアンケートや調査
- 現場での経験から生まれたノウハウ
- 代表や社員の失敗談・成功談
中小企業は、お客様との距離が近く、現場に根ざした経験やストーリーを多く持っています。これらを言語化して発信することは、
- AIO/LLMO/GEO対策としてAIに評価されやすくなる
- 人間の読者にとっても、リアリティのある情報として刺さる
という二重の効果があります。
AIO/LLMO/GEO対策は、決して「難しい横文字のテクニック」だけではありません。 むしろ、
「自社ならではの強みや経験を、分かりやすく丁寧に言葉にしていく」
という、これまでの広報・情報発信の延長線上にあります。 その延長を、AIにも伝わる形に整えていくことこそが、AI時代のWeb戦略と言えるのではないでしょうか。
参考URL
有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content?hl=ja
AI 機能とウェブサイト | Google 検索セントラル
https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features?hl=ja
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。