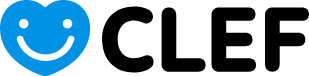応募が増える!クリニック採用サイト成功のポイント

「看護師や医療事務の募集をかけても、なかなか応募が来ない…」 「人材紹介会社に頼むと費用が高すぎて続かない…」
そんな悩みを抱えるクリニックの先生や事務長さんは少なくありません。 実はこの採用の壁は「採用専用サイト(採用特設ページ)」を整えることで、大きく改善できるケースが増えています。
ここ数年で医療従事者の採用市場は様変わりしました。 人材紹介手数料は高止まりし、看護師1名あたりの採用コストが平均70万円を超えることも珍しくありません。 一方で、求職者は求人媒体だけでなく、クリニックの公式サイトやSNSを見てから応募を判断するようになっています。
この記事では、そんな変化に対応するための「採用特設サイトの作り方」と「費用の考え方」を、実際の現場感を交えながらわかりやすくお伝えします。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
目次
1.なぜクリニックに採用特設サイトが必要なのか
1-1.採用コストは年々上昇中
近年、医療業界では採用費の高騰が深刻化しています。
看護師・薬剤師・医療事務など、どの職種も人材紹介会社への依存度が高く、紹介料だけで年間100万円を超えるケースもあります。
- 「ハローワークに出しても応募が来ない」
- 「求人サイトに載せてもアクセスはあるのに応募がゼロ」
そんな声を、頻繁に耳にします。
背景にあるのは、少子化による労働人口の減少と、医療職の慢性的な売り手市場化です。
求職者1人あたりの選択肢が増えた今、ただ求人を“掲載するだけ”では他院に埋もれてしまい、応募に結びつきにくくなっています。
こうした状況の中で、クリニックの特徴や雰囲気を自ら発信し、魅力を伝えることができる採用サイトが採用成功の鍵になっています。
1-2.求職者は“職場の雰囲気”を見ている
最近の求職者は、応募前に必ずといっていいほどクリニックの情報を検索します。
ある調査では、78%の求職者が求人媒体を見たあとに公式サイトをチェックしているという結果が出ています。
特に医療業界では、給与や条件よりも「雰囲気」や「人間関係」を重視する傾向が強く、求人票だけでは伝わらない“職場の空気感”をどう表現できるかがポイントです。
「どんな先生なのか」
「どんなスタッフが働いているのか」
「どんな雰囲気の職場なのか」
これらを伝えることができるのが採用サイトです。採用サイトの開設が応募につながる第一歩になります。
1-3.採用特設サイトで得られる3つの効果
① 採用コストを大幅に削減できる
採用専用サイトを作るには初期費用がかかりますが、人材紹介に比べると長期的には圧倒的に安くなります。
たとえば、看護師2名を人材紹介で採用すると150万円前後。
一方、採用サイトを100万円で制作すれば、翌年以降は追加コストなしで使い続けられます。
年間で数名の採用があれば、2年目以降はコストゼロで採用できる“資産”になるのです。
② ミスマッチを減らせる
求人媒体では「とりあえず応募」する人も多く、面接でギャップが起きやすいもの。
採用サイトでクリニックの方針や働き方を丁寧に伝えておけば、理念に共感した人からの応募が増え、定着率も上がります。
実際に、半年以内の離職率が3分の1に減ったという例もあります。
③ 継続的な採用体制が作れる
採用サイトは24時間働く採用担当者。
求人媒体や紹介会社と併用しながら、長期的な採用の仕組みを作ることができます。
求人掲載が終わってもサイトは残り、いつでも情報を更新できます。
2.応募が集まるクリニック採用サイトの作り方
2-1.「他のクリニックと何が違うか」を明確に
採用サイトで一番大事なのは、“違いを伝えること”。 どこにでもある情報では応募につながりません。
そのためにまず出すべきは、院長先生の言葉です。 求職者は「どんな人のもとで働くのか」を一番気にしています。
「地域に根ざした医療を続けてきた理由」
「スタッフにどんな働き方をしてほしいのか」
「患者さんとどう向き合っているか」
こうした想いを、難しい言葉ではなく先生の言葉で伝えるだけで、サイト全体の印象が大きく変わります。
また、数字や実績を交えて信頼感を高めるのも効果的です。 「開業10年で延べ患者数8万人」「地域健診を5校担当」など、客観的な情報は安心感につながります。
2-2.職種ごとに「刺さる言葉」を変える
看護師と医療事務では、気にするポイントが違います。 職種別ページを作り、それぞれの関心軸でメッセージを出すのが理想です。
看護師向け
- 教育・研修体制(プリセプター制度、勉強会など)
- 子育てとの両立支援(時短勤務・急な休みへの理解)
- 働きやすさ(残業の実態や休暇取得率)
医療事務向け
- 勤務時間の明確さ
- チームワークの良さ
- パート・時短勤務の柔軟さ
「働くイメージ」が湧くほど、応募へのハードルは下がります。
2-3.医療機関ならではのルールにも注意
採用サイトは“広告”として扱われるため、医療広告ガイドラインを守る必要があります。
特に注意したいのは次の3点です。
- 治療効果や他院比較の表現(「○○が治る」「地域No.1」など)はNG
- 患者さんが写った写真やカルテの映り込みは避ける
- スタッフ写真を使う際は本人の同意を得る
信頼を損なわないためにも、撮影や文章表現には十分な配慮が必要です。
医療広告ガイドラインについては以下の記事に詳細を掲載しております。
その他、募集要項を充実させることも非常に大切です。
募集要項の書き方については、以下の記事もご参照ください。
3.求職者が“最終判断”に使う?クリニック採用サイトの役割
3-1.求職活動の中で「最後の確認」に訪れる場所としての採用サイト
採用サイトは、検索で偶然たどり着く場所ではありません。
多くの求職者は、すでに何らかのきっかけでクリニックの名前を知り、「どんな職場なのだろう?」「自分に合う環境だろうか?」と感じた時に訪れます。
その意味で、採用サイトは最初に出会う場ではなく、応募前の最終確認の場です。
たとえば、以下のようなタイミングでアクセスされています。
- 求人サイトで見つけて興味を持ったあと
- 紹介会社や学校の先生から紹介されたあと
- 見学や説明会で話を聞いたあと
- SNSや口コミで名前を目にしたあと
どの場合も共通しているのは、「少し気になっているけれど、もう一歩踏み出す決め手が欲しい」という状態です。
この段階の求職者に対して、採用サイトは「信頼」と「納得」を与える情報源である必要があります。
したがって、採用サイトでは次のような要素を意識して構成すると効果的です。
- 「どんな雰囲気の職場なのか」──写真や動画で視覚的に伝える
- 「自分に合う働き方ができるのか」──勤務体制やサポート制度を具体的に示す
- 「院長やスタッフはどんな人たちなのか」──メッセージやインタビューで人柄を見せる
つまり採用サイトは、“応募を増やすための広告”ではなく、
「関心を持った人が安心して応募に進むための橋渡し」の役割を担っています。
この意識で設計すると、自然と応募率・定着率の両方が高まります。
3-2.スマホで見やすい・押しやすい
求職者の多くはスマートフォンで採用情報を見ています。
そのため、小さな画面でも見やすく、次の行動が直感的に分かる構成が大切です。
文字が読みづらかったり、ボタンが押しにくかったりすると、それだけで離脱につながります。
たとえば「見学予約」や「応募はこちら」などの導線をわかりやすく配置し、どのページからでもスムーズに行動できるようにしておくことが重要です。
また、採用サイトは中途採用の医療従事者だけでなく、看護学生や、これから医療業界を目指す若い世代も見ています。
彼らにとっては、初めて見る職場の印象そのもの。
求人活動の合間や通学中など、ちょっとした空き時間でも気軽に見られるサイトを目指しましょう。
3-3.写真と動画で“職場の空気”を伝える
文章だけでは伝わらないのが「雰囲気」です。
院内の写真やスタッフの笑顔、診療風景などを掲載することで、 働くイメージが自然と湧き、応募への後押しになります。
特に、スタッフ同士のコミュニケーションや休憩中の穏やかな表情など、 日常の一コマにこそ安心感が宿ります。
「この職場なら自分も馴染めそう」と感じてもらえれば、応募のハードルは一気に下がります。
短い動画で1日の流れやスタッフの声を紹介するのも効果的です。
リアルな声や表情が伝わることで、求人票では分からない“人の魅力”を伝えられます。
4.作って終わりにしない。更新できる仕組みがカギ
採用サイトは完成した瞬間がスタートラインです。 求人状況やスタッフ紹介をタイムリーに更新できるよう、院内で更新できる仕組みを整えておきましょう。
求職活動というのはその場で決断をすぐに行うものではなく、長い時間をかけて慎重にエントリーを検討します。そのため、何度かサイトに訪れますので、採用コラムなどが定期的に更新されていたり、新しい情報が掲載されていると、より距離が近づきます。
WordPressなどのCMSを使えば、特別な知識がなくても更新可能です。先述の「採用コラム」以外でも 「募集職種の追加」「スタッフ紹介の更新」「写真の差し替え」などを定期的に行えば、常に“動いているサイト”として信頼されます。
「見たときの情報が古い」だけで、応募をためらう人は多いものです。
また、GA4(Googleアナリティクス4)などのアクセス解析ツールで閲覧数や応募率(コンバージョン率)をチェックし、 「どのページが読まれているか」「どこで離脱しているか」を見ながら改善していくことで、反応率は着実に上がります。
5.クリニック採用サイト制作のまとめ
クリニックの採用難は「人が足りない」ではなく、 「魅力が伝わっていない」ことが原因のケースが多くあります。
採用サイトを作ることで、
- 求職者が安心して応募できる情報発信ができる
- 採用コストを抑えながら継続的な採用が可能になる
- 理念に共感した定着する人材を採用できる
といったメリットが得られます。
人材紹介会社に毎回手数料を払うより、採用サイトを自院の資産として育てる方が、長期的には確実にコストパフォーマンスが高い。
採用で悩む先生こそ、今が「自分たちの採用力を作る」タイミングです。 まずは一歩、採用サイトの整備から始めてみてください。
採用サイトを整えることで、クリニックの魅力を正しく伝え、共感して応募してくれる人材に出会うことができます。
「うちの採用サイトも見直したい」
「一から作りたいけど何から始めればいいか分からない」というクリニックの方は、ぜひ一度ご相談ください。
株式会社クレフでは、医療機関の採用サイト制作に豊富な実績があり、ヒアリングから構成・デザインまで一貫してサポートいたします。
初めての方でも安心して進めていただけるよう、クリニック様の目的とご予算に合わせた最適なプランをご提案いたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的・広告表現上の判断が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。