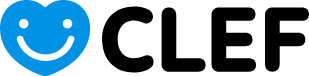採用サイト募集要項の書き方ガイド|法的ルールと応募を増やす実践ポイント【最新版】

(監修:株式会社クレフ 採用マーケティングチーム)
「採用サイトを作ったのに応募が来ない」「応募はあるのに、面接でミスマッチが起きてしまう」
こうした悩みを抱える中小企業の採用担当者は少なくありません。原因の多くは、募集要項の書き方や情報の伝え方にあります。
募集要項は、単なる求人情報の一覧ではなく、求職者にとって企業を知る最初の入り口です。仕事内容や条件が曖昧なままだと、どれほど理念やインタビューを掲載しても、応募者の目に留まりにくくなります。この記事では、数多くの支援実績をもとに、法令を意識した安全な表記と応募につながる伝え方を、具体例とテンプレートで整理します。
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
目次
採用サイトにおける募集要項の重要性とよくあるNGパターン
採用サイトにおける募集要項は、企業と応募者をつなぐ最初の接点です。内容が不十分だと応募につながらなかったり、入社後のミスマッチが発生したりします。
ここでは、実際の相談や行政指導で見かける失敗パターンをまとめました。
パターン1:法令違反に該当する表現
典型例
- 「35歳以下歓迎」「体力に自信のある男性求む」
- 「月給25万円〜」のみで、基本給と手当の内訳が不明
これらは、年齢・性別に関する不適切な表現や、賃金の誤解を招く表示として、是正の対象になる可能性があります。求人内容は広告に該当するため、虚偽や誤認を招く表現は避けることが基本です。
パターン2:内容が簡素で応募につながらない
よくある記載(例)
【職種】清掃スタッフ
【給与】時給1,100円〜
【勤務時間】早朝・深夜あり
【応募資格】やる気のある方
【その他】詳細は面接時に説明
このような記載では、採用サイトを見に来た求職者が仕事内容をイメージできず、応募意欲が高まりません。
以下のように具体化すると、印象が大きく変わります。
改善例
【職種】オフィス清掃スタッフ(未経験歓迎)
【給与】時給1,100〜1,300円(経験による)
【勤務時間】6:00〜9:00/18:00〜22:00(週3日〜OK)
【1日の流れ】6:00出社→6:15清掃→8:30報告→9:00退社
【待遇】交通費支給、制服貸与、社会保険あり(週20時間以上)
求職者が働く姿を想像できる情報を示すことで、応募率が上がるケースは少なくありません。
パターン3:実態とかけ離れた記載による早期離職
- 「残業ほとんどなし」と記載されているが、実態は月40時間前後
- 「充実した研修制度あり」としながら、実際は短期OJTのみ
こうした齟齬は入社後の不信感につながり、早期離職の一因になります。
一方で、「繁忙期は残業月40時間程度、閑散期は定時退社を推奨」など、事実を誠実に伝える企業では、応募数が一時的に減っても定着率は改善する傾向があります。
パターン4:求人媒体と自社サイトの内容不一致
外部の求人媒体と自社サイトで給与レンジや就業時間が異なると、問い合わせ段階で不信感が生まれます。
同一内容・同一更新日に揃える運用が望ましいです。
パターン5:応募導線が遠い・わかりにくい
募集要項の末尾にしかエントリーページへのCTAボタンがない/入力項目が多すぎる――といった導線の摩擦は、応募離脱の大きな要因です。
上・中・下の3箇所に応募ボタンを設置し、所要時間の目安(例:「30秒で簡単応募」)を示すと行動が促されます。
法令に沿った募集要項作成の基本
採用サイトに掲載する募集要項を作成する際は、複数の法令・ルールを意識します。
特に2024年4月の見直しで、募集・採用時に明示が求められる項目が拡充されています。
職業安定法に基づく「募集時の明示事項」
求人広告や採用サイトに掲載する際、次の項目を明示することが求められます(例:職業安定法施行規則第5条)。
2024年改正では、「就業場所・業務の変更範囲」等が追加されました。
参考:e-Gov法令検索(職業安定法施行規則第5条)
必須記載事項
- 業務内容(できるだけ具体的に)
- 契約期間(有期・無期、更新有無)
- 試用期間(期間・試用中の条件変更の有無)
- 就業場所(所在地・転勤の有無)
- 就業時間(始業・終業・休憩・休日、シフトの有無)
- 賃金(基本給と各種手当の区分、固定残業代の有無、支払方法)
- 加入保険(雇用・労災・健康・厚生年金の適用状況)
- 受動喫煙防止措置(屋内禁煙・分煙などの環境)
改正対応項目(2024年4月以降の追加例)
- 就業場所・業務の変更範囲:将来の配置転換・職務変更の可能性
- 更新上限の有無(有期契約):通算期間・更新回数の上限
- 無期転換申込権の説明:勤務開始から一定年数経過後のルール
これらは募集段階での明示を意識します。なお、採用後に交付する労働条件通知書(労基法15条)も、同様に明確な区分と説明が求められます。
参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります」
固定残業代の書き方フォーマット(例)
- 固定残業代:30,000円(月20時間分、超過分は別途支給)
- 内訳の区分:基本給〇〇円+固定残業代〇〇円=総支給〇〇円
- 備考:固定残業代に含まれるのは時間外労働分であり、深夜・休日は別途支給 など
ポイント:時間数と金額、超過分の扱いを明記し、基本給と区分して記載します。
社会保険の記載時の注意
「社会保険完備」などの表現は一般的ですが、適用要件は制度ごとに異なるため、所定労働時間や雇用区分に応じた注記があると安心です(例:「週20時間以上勤務の場合 など」)。
採用サイトの募集要項 記載例(法令準拠のひな型)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
| 試用期間 | 3ヶ月(期間中の条件変更なし) |
| 就業場所 | 大阪市中央区○○1-2-3(転勤なし) |
| 就業時間 | 9:00〜18:00(休憩60分) |
| 休日 | 土日祝、年末年始、夏季休暇(年間休日125日) |
| 賃金 | 基本給:220,000〜280,000円(経験・能力による) 固定残業代:30,000円(20時間分、超過分は別途支給) 通勤手当:実費支給(上限30,000円) 賞与:年2回(昨年度実績3.5ヶ月分) |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
| 受動喫煙防止 | 屋内全面禁煙 |
| 就業場所・業務の変更範囲 | 将来的に関西圏内での配置転換の可能性あり |
| 有期雇用の場合の更新上限 | 通算契約期間〇年/更新回数〇回を上限とする |
| 無期転換に関する取扱い | 勤続5年経過後、本人からの申込みにより無期転換可 |
応募を増やす募集要項の書き方(実務ルール)
- 抽象より具体
NG:「やる気のある方」
OK:「手順を守り、安全に丁寧な作業ができる方」 - 数字で信頼を示す
NG:「残業少なめ」
OK:「月平均残業20時間(繁忙期30時間)」 - 1日の流れを見せる
例:9:00メール確認→10:00商談→13:00資料作成→18:00退社 - キャリア・評価の透明化
例:評価は「業績50%・行動30%・能力20%」。年2回の面談で目標設定。 - 不安を先回りして解消
例:「転勤なし」「在宅勤務週2回可」「未経験者は3ヶ月OJTあり」 - 写真×文章で雰囲気を補完
職場・チーム・設備など3〜5枚を推奨。人物は実在社員・同意取得が基本。 - 導線の摩擦を減らす
応募ボタンは上・中・下に配置。所要時間の目安を明記。
補足:タイトル冒頭に職種・勤務地・給与レンジを置くと、一覧画面でも目に留まりやすくなります。
例:「【大阪・月28〜38万】法人営業(SaaS)/在宅週2日可」
募集要項は他の採用サイトコンテンツへの入口としての役割
募集要項は、単独で完結するコンテンツではありません。採用サイト全体への入口として、重要な役割を果たしています。
募集要項で興味を持った求職者は、次にどのような行動を取るでしょうか。多くの場合、以下のような流れで採用サイト内を回遊します。
- 募集要項で基本情報を確認
- 社員インタビューで実際の働き方をチェック
- 企業理念や事業内容で会社の方向性を理解
- 福利厚生や研修制度で入社後の環境を確認
- 応募フォームへ進む
つまり、募集要項は採用サイト全体のハブ(中心)として機能しているのです。そのため、募集要項から他のページへの導線設計も重要になります。
たとえば、募集要項内に「先輩社員の声はこちら」「研修制度の詳細はこちら」などのリンクを適切に配置することで、求職者の関心に沿って情報を自然に案内できます。
また、募集要項では概要だけを示し、別ページで詳細を紹介する構成も効果的です。
「充実した研修制度あり」と簡潔に記載し、リンク先で具体的な研修内容やキャリア支援制度を詳しく紹介するなど、ページ間の連携を意識した設計が鍵となります。
このように、募集要項を起点とした導線づくりを行うことで、採用サイト全体の回遊率や応募率を高め、結果的に採用活動全体の成果を最大化することができます。
チェックリスト
チェックリスト(公開前の最終確認)
- 法令面:必須項目の明示/表現の適切性(年齢・性別・賃金)
- 整合性:求人媒体・コーポレートサイト・面接台本で齟齬なし
- 具体性:数字・1日の流れ・評価軸・研修の中身が明記されている
- 導線:応募ボタンの配置と所要時間、フォーム項目の最小化
- 更新日:最終更新日を明記(例:「最終更新:2025年11月」)
募集要項に関するよくある疑問(FAQ)
Q1:固定残業代は必須ですか?
A:必須ではありません。導入する場合は時間数・金額・超過分の扱いを明確にし、基本給と区分して記載します。
Q2:未経験者採用で重視すべき点は?
A:研修の具体像・フォロー体制・キャリアの見通しを示すことが重要です。未経験で活躍している社員の事例も有効です。
Q3:ネガティブ情報は書かない方が良い?
A:正直に記載した方が信頼を得やすく、ミスマッチ防止につながります。繁忙期の残業などは、運用上の配慮(例:閑散期の定時退社推奨)も併記します。
Q4:競合の募集要項を参考にしてよい?
A:構成や見出しは参考になりますが、内容は自社独自の実態に合わせて調整します。
Q5:更新頻度は?
A:半期ごと(6ヶ月)を目安に見直しを。法改正・制度変更があった場合はその都度更新します。
Q6:社会保険の記載はどう表現すべき?
A:「適用要件は雇用区分・所定労働時間により異なります」など、一般的な注意書きを添えると誤解を避けられます。
今日からできる採用サイト 3つの改善
募集要項の改善は、大きなコストやシステム変更を必要とせず、今日から始められる最も効果的な採用改善策の一つです。
たった数行の書き換えでも、応募数・応募の質・面接でのマッチ度が変わることがあります。ここでは、すぐに実践できる3つの具体的なステップを紹介します。
1. 「正確で誠実な情報開示」を徹底する
まずは、法令に基づく記載内容の確認と誤解を生む表現の修正から始めましょう。
職業安定法では、業務内容・賃金・就業時間・試用期間などを明確に示す義務があります。
とくに近年は、労働条件の不一致や求人票の虚偽表示に対して、労働局からの指導が増加しています。
たとえば「月給25万円〜」と書いている場合、基本給・手当・固定残業代の区分を追記するだけでも信頼性は大きく向上します。
また、「残業ほとんどなし」「完全在宅可能」などの曖昧な表現は、実態とのズレを招きやすいため、「月平均残業20時間」「在宅勤務:週2回まで」など、数字や条件を具体的に示すことが大切です。
このように「誠実で正確な表記」は、応募者の信頼を得るだけでなく、採用後のトラブル防止にも直結します。
「求人票は企業の顔」と考え、事実を整理したうえで一文ずつ丁寧に書き直してみましょう。
2. 「求職者視点」で情報を再構成する
次に見直すべきは、情報の順番と伝え方です。
募集要項を読む人の多くは、長い説明を読む前に「勤務地」「給与」「仕事内容」の3点をざっと確認しています。
この3要素が冒頭でわかりやすく示されていれば、それだけで応募率は上がります。
たとえば、タイトルの冒頭に
「【大阪・月28万〜】法人営業(SaaS)/在宅週2日可」
といった形で「勤務地×給与×職種」を明示するだけでも、一覧表示の段階で注目されやすくなります。
また、本文の構成は「仕事内容→1日の流れ→待遇→応募資格→職場の雰囲気」というストーリー構成が効果的です。
読んだ人が「自分がここで働くイメージ」を自然に描けるように、
・1日のスケジュール
・具体的な担当業務
・チーム体制(例:3名1チームで進行)
などを加えると、印象がぐっと具体的になります。
さらに、写真や図解も重要な要素です。
言葉だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や設備環境は、3〜5枚の写真で補うことで、短時間でも信頼感を高められます。
求人票は「情報」ではなく「体験の入り口」と捉え、見る人の理解負荷を下げる構成を意識してみましょう。
3. 「定期的な見直し」と「効果測定」を習慣化する
最後に、募集要項は一度作って終わりではなく、運用するものと考えることが大切です。
労働環境・給与体系・福利厚生などは、年単位で変化します。
そのまま放置しておくと、実態と異なる情報が残り、法的リスクや信頼低下につながりかねません。
半年〜1年に一度は、次のような観点でチェックしましょう。
- 表記が最新の制度・条件に合っているか
- 法改正(例:職業安定法・労基法の明示義務)への対応ができているか
- 他媒体(求人サイト・ハローワーク)との内容が一致しているか
- 応募数・応募率・定着率に変化があるか
Google Analyticsや応募フォームのデータを活用すれば、どの職種・どの条件で応募が多いかを可視化できます。
もし応募が少ない場合は、タイトルや写真、給与レンジなどを少しずつ変えてA/Bテストを行うと効果的です。
また、更新日は必ず明記しましょう。
「最終更新:2025年11月」などと記載することで、求職者に「最新情報を発信している会社」という好印象を与えられます。
これは、検索エンジンの評価(SEO)の観点でも有利に働きます。
― 経営者・採用担当者へのメッセージ ―
募集要項の改善は、「採用の最前線を整える」ことに等しい取り組みです。
応募が少ない、離職率が高いと感じたときほど、まずはこの基本に立ち返ることが成果につながります。
小さな修正でも、
- 法令遵守が担保され、安心して応募できる
- 現場との認識のズレが減り、採用の精度が上がる
- 定着率が改善し、採用コストが下がる
こうした中長期的な好循環を生み出すことができます。
まとめ
- 法的要件を満たし、誠実な情報開示を行う
- 求職者の目線で、わかりやすく具体的に構成する
- 定期的に見直し、データに基づいて改善する
この3つを実践するだけで、採用の質と効率は確実に変わります。
募集要項は、企業と人をつなぐ「入口」であり「鏡」です。
今日から少しずつ整えていくことで、理想の人材との出会いが現実のものになります。
参考リンク
無料でお見積り・ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。